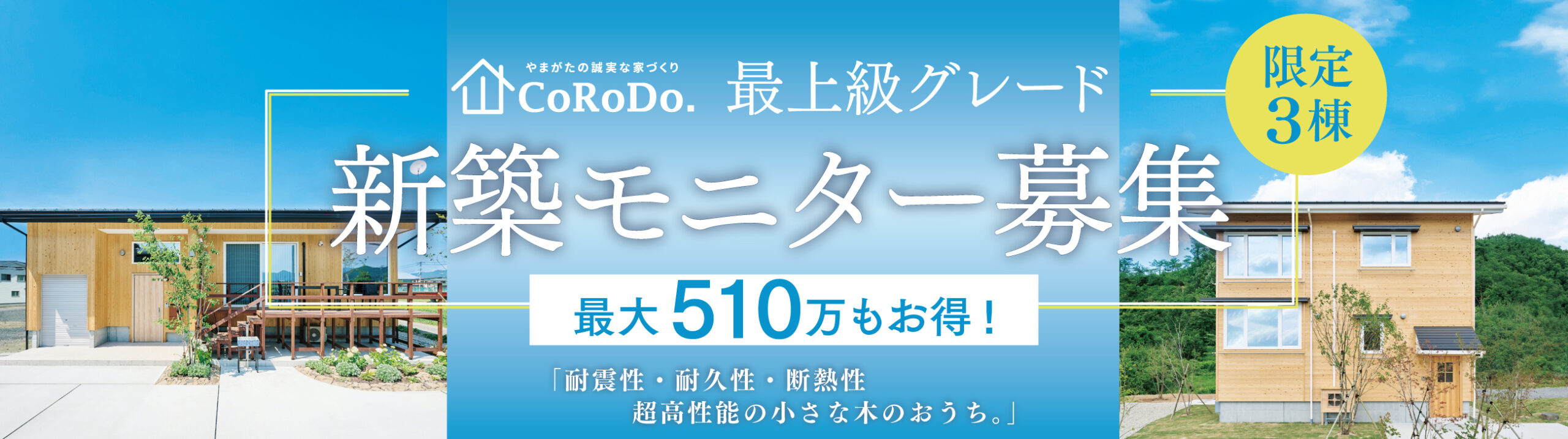家づくりを始めるにあたって、多くの方が悩むのが「収納」の問題です。
見た目や間取りだけでなく、日々の暮らしやすさを左右する収納計画は、快適な住まいづくりに欠かせない重要なポイントです。
特に「収納率」という指標を活用することで、収納の適正な量や配置を客観的に把握しやすくなります。
今回は、収納率の基本的な計算方法から、ライフスタイルに合わせた収納計画の立て方、さらに収納配置の工夫まで、家づくりに役立つ収納の考え方をわかりやすく解説します。
これから新しい住まいを考えている方はぜひ参考にしてみてください。
家づくりの収納計画
収納率の計算方法
収納率とは、住宅の延床面積に対する収納スペースの面積の割合です。
計算方法は、収納面積 ÷ 延床面積 × 100 で求めることができます。
例えば、延床面積が120㎡で、収納面積が12㎡の場合、収納率は 12㎡ ÷120㎡ × 100 = 10% となります。
収納面積には、クローゼットや押入れなどの床から天井まで使える収納スペースを含みます。
ただし、キッチンカウンター下収納や、床下収納などは、一般的には含まれません。
正確な計算には、設計図面を確認することが重要です。
適正な収納率とは
一般的に、マンションでは8~10%、戸建て住宅では10~15%が適正な収納率とされています。
しかし、これはあくまで目安です。
家族構成やライフスタイル、持ち物の量によって、必要な収納量は大きく異なります。
例えば、趣味で多くの道具を使う方や、衣類を多く所有する方は、より高い収納率が必要となるでしょう。
逆に、ミニマリストの方は、低い収納率でも十分な場合もあります。
生活スタイルをしっかりと見極め、自分にとって適切な収納率になっていそうかどうかを検討することが大切です。
ライフスタイル別収納計画
収納計画は、単に収納率だけを考えるのではなく、ライフスタイルに合わせた計画が重要です。
例えば、小さな子どもがいる家庭では、おもちゃやベビー用品を収納するスペースを十分に確保する必要があります。
また、テレワークをする家庭では、書斎やワークスペースの収納も考慮しなければなりません。
家族構成や生活スタイルを具体的に想像しながら、各部屋に必要な収納の種類や量を検討していきましょう。
例えば、キッチンにはパントリー、洗面所にはリネン庫などを計画的に配置することで、使い勝手の良い収納を実現できます。
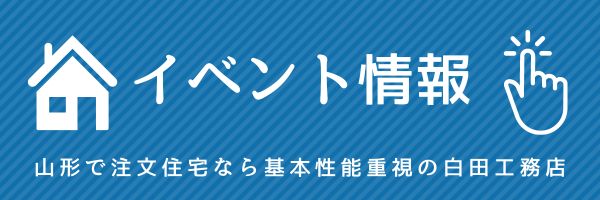
収納率活用術と家づくり
収納率の算出と活用
収納率を計算することで、アパートなどの現在の住まいの収納状況を客観的に把握し、新居の収納計画に役立てることができます。
現在の住まいでは収納が不足していると感じている場合、新居では収納率を高めることを検討しましょう。
一方で、収納が多すぎてスペースが余っていると感じている場合は、収納率を下げたりする必要があるかもしれません。
収納率は、家づくりの重要な指標として、積極的に活用しましょう。
収納配置と効率化
収納率だけでなく、収納の配置や効率性も重要です。
収納を集中させる「集中型」と、各部屋に分散させる「分散型」の2つのタイプがあります。
集中型は、大きな収納スペースを1か所に設けるため、収納率を高めやすい反面、収納スペースまで移動する手間がかかります。
分散型は、各部屋に小さな収納スペースを設けるため、動線が短く、使いやすさが向上しますが、収納率は低くなる傾向があります。
どちらが良いかは、ライフスタイルや間取りによって異なります。
集中型と分散型の比較
集中型は、ウォークインクローゼットや納戸など、大きな収納スペースを1か所に集約する方式です。
収納率は高くなりますが、頻繁に使用するものは出し入れが面倒になる可能性があります。
一方、分散型は、キッチン、洗面所、各居室などに、必要な場所に必要な収納スペースを配置する方式です。
収納率は低くなる可能性がありますが、使いやすさが向上します。
それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身のライフスタイルに合った収納計画を立てましょう。
例えば、1階に生活用品を収納する分散型収納をメインにし、2階には季節物などを収納する集中型収納(ロフトなど)を設けるといった組み合わせも有効です。
建築費の高騰による家の狭小化
近年、土地の分譲価格や住宅の建築費が急激に高騰しています。
土地や建築費が上がる一方で、働く人たちの手取り給与は良くて横ばいのため、家づくりの予算はそれほど増えていません。
つまり、土地や家を従来より小さくして、予算になんとか収めることが必要になってきているのです。
家が小さくなる一方で、住む人の人数や収納する必要のある物の量はそれほど大きく減ってはいません。
そうすると、これまで一般的であった収納率では収納のスペースがまったく足りず、生活が破綻してしまうリスクが出てきているのです。
たとえば、先ほどの120㎡の家の例では、収納率10%だと収納量は12㎡でした。
建築費は数年前と比べて3~5割程度も高くなっていますから、同じ予算だと90㎡程度の家が限界かもしれません。
90㎡の家で収納率10%だと収納量は9㎡になってしまいます。
このわずかな収納量ではすぐにいっぱいになってしまい、まともに生活することが難しくなってしまいます。
今後家が狭小化していく中では、収納率を多めに見込むことが重要になっていくでしょう。
弊社としてはその解決策として、高基礎によって生まれる床下の余剰空間を床下収納として利用することを推奨しています。
狭小化する住まいでは、家を立体的に利用し尽くす必要があるのです。
床下収納の魅力を体感いただくための見学会なども開催していますので、ぜひお気軽にご予約いただけると幸いです。
床下収納見学会
https://www.ie-miru.jp/cms/yoyaku/shiratakomuten/events/88272

まとめ
今回は、家づくりの収納計画において重要な「収納率」について、計算方法、適正な数値、そしてライフスタイルに合わせた収納計画の立て方、収納配置の効率化について解説しました。
収納率はあくまでも目安であり、家族構成や生活スタイル、持ち物の量などを考慮して、最適な収納計画を立てることが大切です。
収納率だけでなく、収納の配置や使いやすさも考慮し、快適な住まいを実現しましょう。
また、今後も狭小化していく戸建て住宅では、収納不足による生活の破綻を回避するために、収納率を高めに見込むことが必要になってきます。
また、家を立体的に利用し尽くすこともぜひ検討していきましょう。
後悔のない家づくりに向けて、ぜひこの記事を参考にしてください。
快適な収納空間を手に入れて、充実した毎日を送りましょう。
山形で注文住宅を建てるなら白田工務店へお任せください!
白田工務店では「基本性能重視」の家づくりを大切にし、安全・安心、長持ち、健康・快適・省エネの3つの視点から、お客様に価値のある住まいをご提案しています。耐久性が高く、高気密・高断熱で省エネにも優れ、夏の暑さや冬の寒さが厳しい山形でも快適に暮らせる家づくりをお手伝いします。
「一生に一度の家づくり」だからこそ、デザインだけでなく、住み続けるほどに実感できる快適さと性能を重視し、ご家族の未来を支える住まいをご提案します。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
電話でのお問い合わせはこちら:0237-83-9522(受付時間 8:00~17:30/日曜定休)
WEBからのお問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム(24時間受付)
モデルハウスについて:モデルハウス詳細ページ