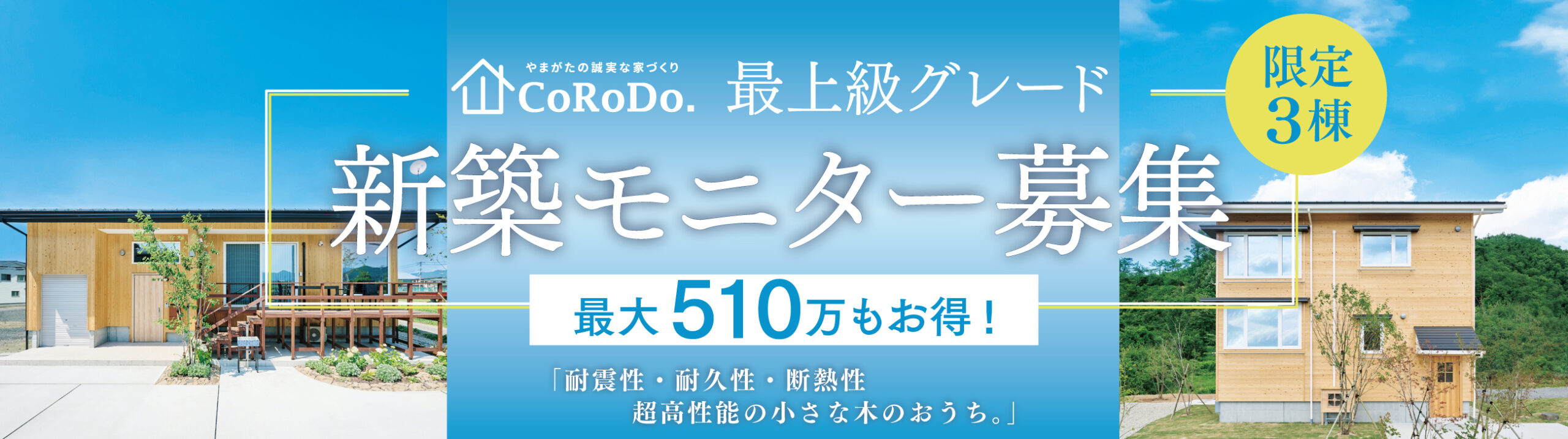近年多発している大きな地震。
山形県内にも大きな断層があり、災害級の地震が身近でいつ起こるか分かりません。
大切な家族を守るため、そして安心して暮らすために、地震に強い家づくりは欠かせません。
多くの人が「地震に強い家」を望んでいますが、その具体的な方法については、まだ十分に理解されていないのが現状です。
そこで今回は、地震に強い間取りを実現するための具体的な方法について見ていきましょう。
地震に強い家の間取り
総二階の直方体の家
地震の揺れは、建物の形状によっても影響を受けます。
複雑な形状の建物は、揺れの力が特定の部分に集中しやすく、損傷や倒壊のリスクが高まります。
一方、長方形・正方形の間取りをもった、直方体のようなシンプルな形状は、揺れの力を均等に分散させるため、地震に強いと言われています。
そのうえ総二階(1階と2階の面積が同じ)の建物は、上下のバランスがとりやすいので柱や壁の直下率を上げやすく、ねじれによる被害を軽減する効果が期待できます。
総二階で直方体の家は耐震性の高さだけでなく、コストパフォーマンスにも優れています。
外壁の面積が少なくなるため外皮性能も安定しやすく、断熱や気密の施工精度も確保しやすいのが特徴です。
また屋根や基礎の形状もシンプルになるため、建築コストを抑えながら高性能な住宅を実現できます。
結果として、長期にわたって安心して暮らせる住まいにつながるのです。
<関連記事>
過去のブログ記事でも総二階の家についてご紹介をしているので、こちらもぜひ読んでみてくださいね!
耐力壁の配置とバランス
耐力壁は、耐震構造における重要な要素です。
耐力壁の配置は、建物の形状や開口部の大きさによって最適なバランスが異なります。
耐力壁が多すぎても少なすぎてもバランスが悪くなり、地震への抵抗力が低下する可能性があります。
重要なのは、耐力壁をバランス良く配置し、建物の重心と剛心のずれ(偏心率)を小さくすることです。
耐力壁の適切な配置場所は構造計算により割り出され、大工さんたち職人による正確な施工と細かい施工管理により、より高い耐震性を確保することができるのです。
耐力壁の設置は単に量を増やせばよいのではなく、建物全体のバランスを考慮することが不可欠です。
例えば一方向にだけ壁が偏ると、地震時にねじれを生じ、かえって被害を拡大させる恐れがあります。
設計段階で構造計算を十分に行い、偏心率を小さく抑えることが重要です。
これは建築完了後にどうこうできることではありませんので、しっかり計画段階から構造計算(許容応力度計算)によって耐震を検討し、施工時にも仕様通り・設計通りの施工ができているかといった施工管理がすべてを決めることになります。
開口部の大きさの注意点
大きな開口部は、地震時に大きな力が加わる部分です。
窓やドアなどの開口部を大きく設計する場合は、その分耐力壁を増やすか、より強い建材を使用するなど、適切な対策が必要です。
複雑な形状のリスク L字型やコの字型など、複雑な形状の建物は、地震の揺れが特定の部分に集中しやすく、損傷や倒壊のリスクが高まります。
また、凹凸が多い形状も、揺れによってねじれが生じやすいため注意が必要です。
シンプルな形状にすることで、地震の力を分散し、建物の安全性を高めることができます。
大きな窓や吹き抜けを取り入れると、開放感や採光性が増して暮らしやすさは向上しますが、その一方で耐震性には慎重な配慮が必要です。
例えば、耐力壁を減らさざるを得ない間取りでは、代わりに耐震フレームや強化梁を活用する設計が求められます。
また、ガラス部分を複層ガラスや合わせガラスにすることで、割れにくさや安全性を高める工夫も可能です。
見た目のデザインを優先する際には、必ず構造計算と併せて検討し、デザインと強さを両立させることが大切です。
例えば弊社のモデルハウスや建築事例では、コーナーサッシを積極的に取り入れています。
「建物の角は耐力壁を入れた方が良い」というのが住宅建築での定説ではありますが、しっかり構造を検討しさえすれば、建物の角の両側に窓サッシを配置しても問題のない設計が実現できます。
「構造計算をしなければならない」と聞くと、間取りに制限を与えるだけのような嫌なイメージを持たれるかもしれませんが、逆に実現したいデザインや窓配置を成立させるための心強い武器にもなりうるとお考えください。
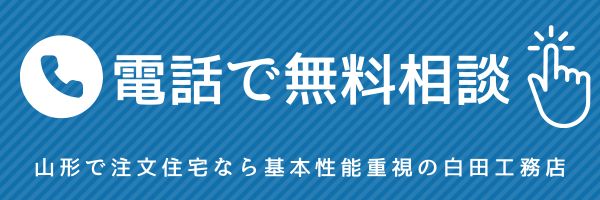
地震に強い家づくりの対策
基礎の重要性と施工精度
基礎は、建物の重量を支え地面に伝えるために、建物の一番下に位置する重要な構造体です。
地盤の状況に合わせて適切な基礎を選択することが重要です。
地盤調査を行い、その結果に基づいてベタ基礎、布基礎など適切な基礎工法を選択する必要があります。
また、基礎の鉄筋の配筋やコンクリートの厚み、施工精度にも注意を払う必要があります。
構造計算で耐震等級3の作りにしているからといっても、施工がテキトーであれば想定通りの強度・耐力を得ることはできません。
施工管理を徹底し、正確な施工をしていく必要があるのです。
基礎工事の精度は、地震に強い家づくりの根幹をなすものです。
鉄筋のかぶり厚やコンクリートの打設方法に不備があると、強度不足やひび割れの原因になります。
施工現場では配筋検査やコンクリート試験をしっかり行い、第三者機関によるチェックを受けるとより安心です。
耐震等級の数値を満たすだけではなく、実際の施工品質を高めることで初めて「本当に地震に強い基礎」が実現します。
適切な工法の選択
木造住宅と一口に言っても、在来工法、金物工法、SE構法など、様々な工法があります。
それぞれの工法には、耐震性やコスト、設計の自由度などに違いがあります。
建物の規模や形状、予算などを考慮し、最適な工法を選択することが重要です。
工法の選択は耐震性だけでなく、将来のメンテナンス性やライフスタイルにも影響を及ぼします。
在来工法は自由度が高く増改築に向き、SE構法は大空間を実現しながら耐震性を確保できます。
金物工法は安定した強度を発揮しやすく、耐久性にも優れています。
どの工法にも一長一短があるため、建物の形状や予算、家族の暮らし方を踏まえて選択することが求められます。
耐震診断と補強工事
既存住宅の場合、耐震診断を行うことで、建物の耐震性を評価することができます。
診断結果に基づいて、必要な補強工事を検討する必要があります。
補強工事には、耐力壁の増設や筋交いの設置など様々な方法があります。
耐震診断は自治体の補助制度を活用できる場合があり、費用を抑えて実施可能です。
診断では壁量、基礎の状態、劣化の有無などを総合的にチェックし、その結果に応じた補強プランを立てます。
補強工事は外壁を壊さずに行える方法もあり、住みながらでも施工可能なケースがあります。
大地震に備えるためには、診断と補強を組み合わせて早めに対策を講じることが安心につながります。

まとめ
地震に強い家づくりは、間取り、構造、基礎など、様々な要素が複雑に絡み合っています。
総二階の直方体の家に近いシンプルな間取り、バランスの良い耐力壁の配置、適切な基礎工法の選択などが重要です。
安全で快適な住まいを実現するためには、綿密な計画と丁寧な施工が不可欠です。
地震への備えは、日々の生活の安心と安全を守る第一歩です。
山形で注文住宅を建てるなら白田工務店へお任せください!
白田工務店では「基本性能重視」の家づくりを大切にし、安全・安心、長持ち、健康・快適・省エネの3つの視点から、お客様に価値のある住まいをご提案しています。
耐久性や耐震性が高く、高気密・高断熱で省エネにも優れ、夏の暑さや冬の寒さが厳しい山形でも快適に暮らせる家づくりをお手伝いします。
「一生に一度の家づくり」だからこそ、デザインだけでなく、住み続けるほどに実感できる快適さと性能を重視し、ご家族の未来を支える住まいをご提案します。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
電話でのお問い合わせはこちら:0237-83-9522(受付時間 8:00~17:30/日曜定休)
WEBからのお問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム(24時間受付)
モデルハウスについて:モデルハウス詳細ページ