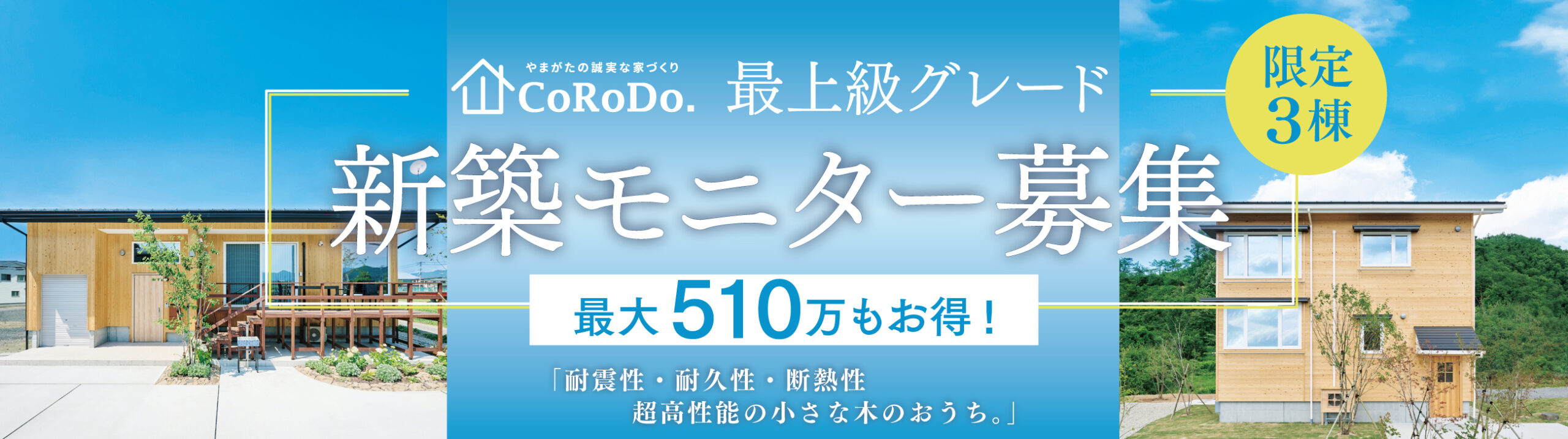家の顔ともいえる玄関は、家族や来客を最初に迎える重要な空間です。
その玄関の印象を大きく左右する要素の一つに、上がり框(がまち)があります。
しかし、その必要性やデザイン性については、意外と知られていないかもしれません。
今回は、玄関の上がり框を多角的に解説します。
玄関の上がり框の機能・デザイン
機能性
上がり框は玄関の三和土と室内との段差を区切るための横木ですが、その役割は多々あります。
玄関の雰囲気をよくしたり格式高く魅せることができます。
また、外部からの土や砂が室内に入ることを防ぐ機能もありますし、靴を脱ぎ履きするときに腰掛ける場所としても使用できます。
印象や機能性は玄関の広さ、上がり框の高さ、使用する素材など、色んなことを総合的に検討することで、納得のいく玄関を作ることができるでしょう。
デザイン性の向上
上がり框は、玄関のデザイン性を高める重要な要素です。
素材(木材、石材、タイルなど)は、耐久性、メンテナンス性、デザイン性を考慮して選びましょう。
形状は、玄関の広さや動線、収納との関係性などを考慮して決定します。
直線的な形状はシンプルで、どんなスタイルにも合わせやすいです。
一方、曲線的な形状は、より個性的で柔らかな雰囲気を演出します。
L字型などの形状は、空間を有効活用したい場合に適しています。
これらの要素を総合的に判断し、最適な素材と形状を選びましょう 例えば、天然木の温かみのある上がり框は、落ち着いた雰囲気を演出します。
一方、大理石や御影石の上がり框は、高級感とスタイリッシュさをプラスします。
素材や形状を工夫することで、個性的で魅力的な玄関空間を創り上げることが可能です。
素材選びの際には、耐久性やメンテナンスの容易さも考慮しましょう。

玄関の上がり框の適切な高さ
適切な高さの選び方
上がり框の高さは、安全性と使い勝手の両面から慎重に検討する必要があります。
高齢者の安全性を考慮すると18cm以下が理想的ですが、デザイン性や玄関の構造によっては、異なる高さを選ぶ場合もあります。
また、既存の住宅のリフォームを行う場合は、現在の高さを参考に、必要に応じて手すりや式台などを追加することで、より快適な玄関を実現できます。
高齢者への配慮
上がり框の高さは、高齢者の安全と快適性に直結します。
昔のお家(古民家など)では高い位置に上がり框があり、手前に式台などがあって階段のような様式もありましたが、現代の上がり框は低い位置に設置することが通常です。
国土交通省は、高齢者の居住安定確保のため、戸建て住宅では18cm以下を推奨しています。
これは、高齢者が上がり框を昇り降りする際の負担を軽減し、転倒リスクを低減するためです。
しかし、18cmを超える場合は、手すりや式台を設置することで安全性を確保できます。
手すりの高さは、使用者の身長に合わせて調整することが重要です。
また、式台は上がり框までの高さを低くし、靴の脱ぎ履きを容易にします。
これらの工夫によって、高齢者も安心して玄関を利用できるようになります。

まとめ
今回は、玄関の上がり框について、機能性、デザイン性、高齢者への配慮といった多角的な視点から解説しました。
上がり框の高さ、素材、形状は、安全性、使い勝手、デザイン性という様々な要素が絡み合って決定されます。
新築・リフォームにおいては、これらの要素を総合的に考慮し、ライフスタイルや家族構成に最適な選択をすることが大切です。
快適で安全、そして美しい玄関を実現するために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
山形で注文住宅を建てるなら白田工務店へお任せください!
白田工務店では「基本性能重視」の家づくりを大切にし、安全・安心、長持ち、健康・快適・省エネの3つの視点から、お客様に価値のある住まいをご提案しています。耐久性が高く、高気密・高断熱で省エネにも優れ、夏の暑さや冬の寒さが厳しい山形でも快適に暮らせる家づくりをお手伝いします。
「一生に一度の家づくり」だからこそ、デザインだけでなく、住み続けるほどに実感できる快適さと性能を重視し、ご家族の未来を支える住まいをご提案します。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
電話でのお問い合わせはこちら:0237-83-9522(受付時間 8:00~17:30/日曜定休)
WEBからのお問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム(24時間受付)
モデルハウスについて:モデルハウス詳細ページ