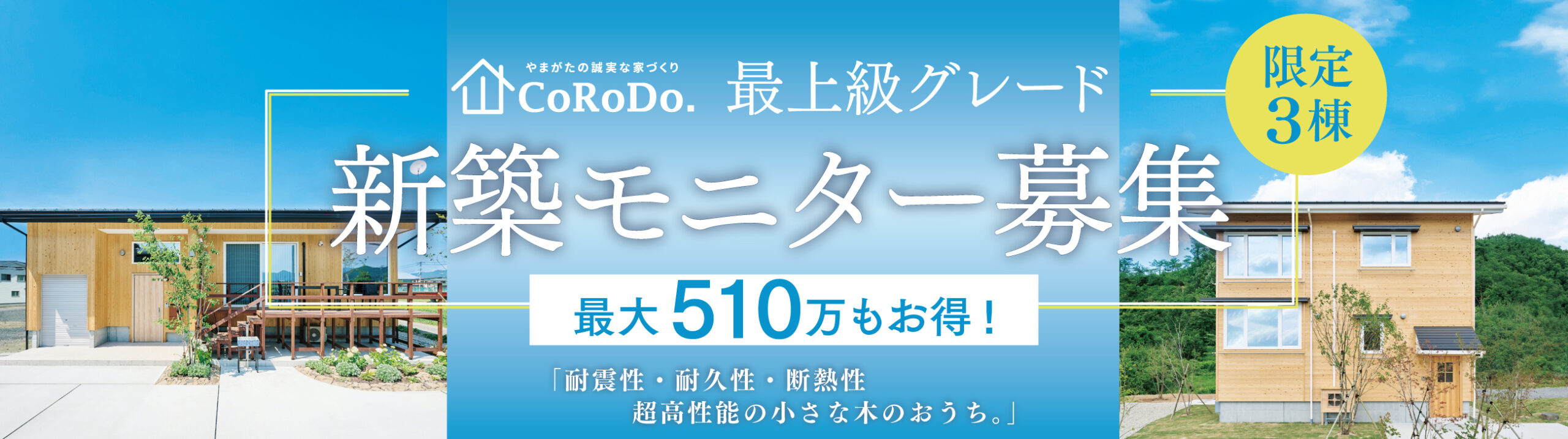これから家を建てることを検討している方の中には、性能にこだわって、理想の家を建てたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
家を建てる上で、C値、UA値、Q値といった住宅性能に関する用語を耳にする機会も多いです。
これらの数値は、家の性能を表す重要な指標ですが、それぞれの意味や基準値を理解していないと、性能の良い家を建てることは難しいでしょう。
そこでこの記事では、C値、UA値、Q値の意味をわかりやすく解説します。
C値・UA値・Q値とは?住宅性能を表す3つの指標
C値、UA値、Q値は、住宅の気密性や断熱性を表す指標であり、それぞれ数値が小さいほど高性能であることを示します。
1:C値(相当隙間面積)
家のすき間の大きさを表す指標です。
単位は[㎠/㎡]で表され、「住宅の床面積1㎡あたり、何㎠の隙間があるか」ということを表しています。
数値が小さいほど、すき間が少なく、外気の影響を受けにくいことを意味します。
例えばC値1.0とは、30坪ほどの家全体ではがき1〜2枚分程度の隙間があるイメージです。
C値0.5以下になると、その隙間はさらに半分以下となり、冷暖房効率の違いを体感しやすくなります。
例えばUA値0.34と0.28を比べると、年間の冷暖房費に数万円単位の差が出ることがあります。
特に窓や天井・屋根の断熱性能を高めることでUA値は大きく改善でき、冬の寒さや夏の暑さを和らげる効果があります。
2:UA値(外皮平均熱貫流率)
家の熱がどれくらい逃げるかを表す指標です。
単位は[W/㎡・K]で表され、「住宅の外皮面積からどれくらい熱が逃げていきやすいか」ということを表しています。
数値が小さいほど、熱が逃げにくく、暖房効率が良くなることを意味します。
3:Q値(熱損失係数)
UA値と同様に家の熱がどれくらい逃げるかを表す指標ですが、UA値と大きく異なる点は、換気による熱損失も考慮している点です。
数値が小さいほど熱が逃げにくく、冷暖房効率が良くなることを意味します。
建築業界の中でも意外と知られていませんが、Q値には「旧Q値」と「新Q値」が存在します。
旧Q値の計算では換気による熱損失が換気機器ごとに変わりますが、新Q値においては換気による熱損失は定数として計算することになっているため、計算結果はまったく異なるものとなるのです。
これは2013年10月施行の新省エネ法より変更されています。
換気システムの種類や性能によっても数値に影響があり、高性能にすると旧Q値改善につながります。
性能の良い換気システムを選択することで、快適性と省エネの両立が可能になるでしょう。
旧Q値なのか新Q値なのかを明記せずに、「当社のQ値は~です。」とアピールしている会社さんも多いため、Q値で複数事業者間の性能比較をするのはイマイチ当てにならないと考えた方が良いかもしれません。
例えば、新住協という団体では、このQ値(旧Q値)1.0以下を目指す「Q1.0住宅(キューワン住宅)」を積極的に推進しています。
こういう団体に所属されている事業者さんの中であれば、計算方法が統一されているはずですから比較はしやすいかもしれませんね。
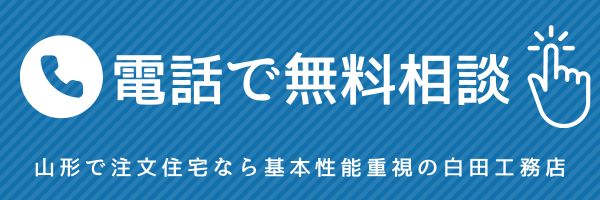
C値・UA値・Q値はどのくらいが理想?性能の基準値を解説
C値、UA値、Q値にはそれぞれクリアすべき基準と現状の最高基準があります。
ただ、この基準はお家を建てる地域によって基準が異なり、山形県内の地域は全国的に見ても高い性能基準が求められます。
1:C値
C値は気密性能を表す基準です。
とはいえ国の定める基準は現在廃止されていますので、どのあたりを基準にすべきか分かりづらいかもしれません。
ですが例えば山形県が独自に定める「やまがた省エネ健康住宅」の認定基準としては、C値1.0以下を条件としています。
そのほか、北海道札幌市が独自に定める「札幌版次世代住宅基準」の令和5年度改定版からは、ブロンズ~プラチナの4グレードすべてにおいて、新築住宅ではC値0.5以下を認定条件としています。
以前はミニマムレベル~トップランナーレベルの5グレードのうち、上位2グレードはC値0.5以下、下位3グレードはC値1.0以下を認定基準としていました。
このことからC値の基準としては、 1.0以下であれば通常の高気密住宅、 0.5以下であればハイレベルな高気密住宅、 といえるでしょう。
一般的な新築住宅ではC値1.0前後が多いですが、気密測定を実施することで確実な数値を確認できます。
C値は施工の丁寧さに直結するため、技術力の高い施工会社選びの指標にもなります。
2:UA値
UA値は断熱性能を表す基準です。
断熱性能については国の断熱性能等級によって最高等級の等級7まで基準が定められていますので、そちらを参考にするのが良いでしょう。
2025年度からは等級4が義務化され、 2030年度からは等級5が義務化されるのでは、と言われております。 そこから考えれば、等級5をクリアしているのは当たり前。
今後は等級6以上をクリアして初めて「高断熱住宅」と胸を張って言える時代となっています。
断熱性能UA値は地域によって求められる基準値が異なってきます。
山形県の大部分は省エネ基準地域区分上の4地域に該当し、一部はより寒冷な3地域に該当しますので、そちらで考えてみましょう。
3地域での等級6はUA値0.28以下、等級7は0.20以下となっています。
4地域での等級6はUA値0.34以下、等級7は0.23以下となっています。
他にも参考になる基準値は様々ありますが、今回の記事ではこの程度にしておきましょう。
上記の数値基準を参考に言えば、山形県においては、 UA値0.34以下が高断熱住宅、 UA値0.23以下が超・高断熱住宅、 と考えるのがこれからのスタンダードと言えるでしょう。
UA値は「家全体の平均値」なので、一部の窓や壁が弱いと数値全体が悪化します。
特に窓は熱が逃げやすいため、性能の高いガラスやサッシを選ぶと数値改善に直結します。
3:Q値
Q値はかつて国が断熱性能を表すのに使用していた基準ですが、現在は廃止されておりますので明確な基準はありません。
先述で少し紹介した新住協という団体では、断熱性能を重視した家づくりをおこなっており、Q値1.6以下がおおむね高性能、1.0以下が超・高性能といわれているようです。
新住協という断熱性能を重視した家づくりをおこなう団体では現在もQ値を重視した家づくりをおこなっており、おおむね1.6以下が高性能、1.0以下が超・高性能といわれているようです。
Q値1.0を達成した家はQ1.0(キューワン)住宅と呼ばれ、ここを目指した家づくりをおこなっています。
Q値は今は公式基準ではないものの、実際の快適性をよく表す指標です。
例えば、外気温が0℃でもQ値1.0の家なら少ない暖房で室内20℃を保ちやすく、ランニングコスト削減にもつながります。
これらの基準値を参考に、自分にとって最適な性能の家を検討しましょう。
しかし、C値、UA値、Q値をただ基準値よりも小さくすれば良いというわけではありません。
大切なのは、これらの数値と快適性やコストなどを総合的に判断し、自分にとって最適な性能の家を選ぶことです。

まとめ
この記事では、C値、UA値、Q値の意味と基準値について解説しました。
これらの数値は、家の性能を表す重要な指標であり、家を建てる際には必ず確認するようにしましょう。
数値の良し悪しだけに注目せず、「敷地条件に合っているか」、「新居でどんな時間を過ごしたいか」など、住まいを広い視座で捉えましょう。
「自分たちにとっての良い家」を追求することが、心から納得できる家づくりのポイントです。