日本の住宅事情は、時代やライフスタイルの変化とともに大きく変遷しています。
限られた土地の中で、いかに快適で豊かな生活空間を確保するかが、多くの世帯にとって重要な課題となっています。
戸建て住宅を検討する際、まず最初に頭を悩ませるのが、その広さ、つまり坪数ではないでしょうか。
理想の住まいを実現するためには、平均的な坪数だけでなく、様々な要素を考慮した上で、最適な広さを選択する必要があります。
そこで今回は、日本の戸建て住宅の平均坪数とその背景を分析し、家づくりのヒントとなる情報を提供します。
日本の家の平均坪数
1:全国平均と地域差の比較
日本の戸建て住宅の平均坪数は、地域によって大きく異なります。
住宅金融支援機構のフラット35利用者調査によると、最新データである2023年度の結果では、注文住宅の全国平均の床面積は119.5㎡(36.14坪)とされています。
都市部では土地価格の高騰から、全国平均より小さくなる傾向があります。
一方、地方では比較的広い土地が確保できるため、平均坪数が大きくなる傾向が見られます。
具体的な数値は、調査機関や調査時期によって異なるため、複数のデータを参照することが重要です。
例えば、北海道では広大な敷地を活用したり、積雪や寒冷地対策をするために、全国平均よりも広い面積の住宅が建てられる傾向があります。
2:平均坪数の推移と将来予測
過去数十年のデータを見ると、日本の戸建て住宅の平均坪数は、時代の変化を反映して推移してきました。
高度経済成長期には、広い住宅が好まれる傾向が強まりましたが、近年はコンパクトな住宅への需要が高まっています。
少子高齢化や核家族化、ライフスタイルの変化、土地価格の高騰などが、この傾向を後押ししています。
前述の住宅金融支援機構の利用者調査にて、2023年度の注文住宅の全国平均は119.5㎡(36.14坪)と紹介しました。
例えばその5年前の2018年度の利用者調査を見ると126.8㎡(38.35坪)ですから、たった5年で2坪強も家が小さくなっていることが分かります。
特に2022年度までと比べて2023年度のグラフの下がり方が大きいのがお分かりでしょうか。
様々な要因が重なっているかとは思いますが、特に大きな要因としては、ウッドショック、半導体ショック、円安ドル高の進行、などが挙げられるでしょう。
世界的な経済の動向が日本の住宅価格を押し上げ、一方で消費者の収入は変わらず予算が上がらないため、コスト低減のため家が小さくなっていく、という大きな流れがあります。
様々な要因が複雑に絡み合っているため、断定的なことは言えませんが、今後円高ドル安に大きく振れて資材高騰が落ち着いたとしても、省スペース化技術の進歩や多様な住まい方の普及によって、平均坪数は大きく増えることはなく、30坪付近をめがけて減少していく可能性が高いものと考えられます。
3:家族構成と適切な坪数の関係
適切な坪数は、家族構成によって大きく異なります。
夫婦二人暮らしであれば、コンパクトな30坪程度の住宅でも十分な広さと言えるでしょう。
むしろ広すぎるという考えもあります。
子供がいる世帯では、個室の確保や共有スペースの確保が必要となるため、子供の数次第では少々手狭に感じる可能性もあります。
国土交通省のデータでは、家族構成別の推奨延床面積が示されており、目安として活用できます。
ただし、これはあくまでも目安であり、家族の生活スタイルやライフプラン、予算などに合わせて、適切な坪数を検討する必要があります。
特にお伝えしておきたいのが、子供はいつまでも親と一緒に住み続けるわけではない、ということです。
子供が3人いるからと子供部屋を3つ作ったところで、十数年後に子供が巣立ってそれぞれの所帯を持てば、空いた子供部屋は物置になるだけなのです。
子供と一緒に暮らす時間より、子供が巣立った後の時間の方が長い可能性が高いのです。
それを念頭に置き、今後は必要最低限の坪数、山形県内でもおよそ30坪前後を目安に住宅を新築することを、当社では推奨しています。
その際、坪数の小さい家は収納の量が足りずに生活が破綻してしまうリスクもはらんでいます。
その点当社では、家を小さくしつつ、充分な収納量を確保できる家づくりをご提案していますので、ぜひお尋ねください。
4:土地面積と予算との兼ね合い
住宅を建てる際には、土地面積と予算を考慮することが不可欠です。
土地面積が限られている場合は、坪数を小さくせざるを得ないケースも出てきます。
また、予算が限られている場合は、坪数を小さくしたり、間取りやデザイン、建材を工夫したりするなど、コスト削減策を講じる必要があります。
土地価格や建築費は地域差が大きいため、希望の坪数と予算を両立できるかどうかを、綿密に計画する必要があります。
土地の購入費は、全体の30~40%程度を目安とすることが多いですが、地域や立地によって大きく変動します。
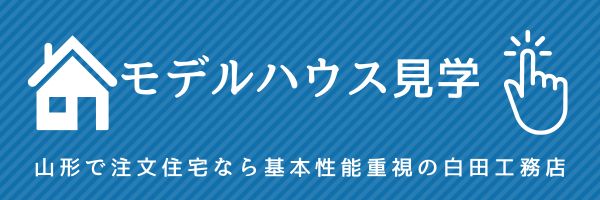
平均坪数に影響する要因の分析
1:土地価格の高騰の影響
土地価格は、住宅の坪数に大きな影響を与えます。
特に都市部では、土地価格の高騰が顕著であり、住宅価格全体を押し上げる要因となっています。
近年は地方でも土地価格の上昇が見られる地域が出てきています。
そのため、全国的にコンパクトな住宅が好まれる傾向が強まっています。
2:住宅性能の向上と省スペース化
近年、住宅の断熱性能や気密性能が向上しており、省エネルギー住宅が普及しつつあります。
高性能な窓や断熱材を使用することで、暖房や冷房の効率を高め、エネルギーコストを削減できます。
断熱性能の向上は、今後もずっと続くであろう電気代の高騰対策に対して非常に有効です。
政府は電気代の上昇は年3%のペースで続く見通しとしています。
この電気代の内訳を見ると、特に大きくかかるのは給湯代と暖房代です。
暖房代を抑えるには、そもそも暖房が必要な広さを削減するということも重要です。
コンパクトな住宅は省エネ住宅の1つの手段でもあるのです。
それに、省スペース化技術も進歩しているため、工夫次第ではコンパクトな空間でも満足のいく生活が可能です。
例えば、収納家具や可動間仕切りなどを活用したり、空間を立体的に利用して収納量を増やすことで、限られたスペースを有効に活用できるようになっています。
3:ライフスタイルの変化と住空間のニーズ
ライフスタイルの変化も、平均坪数に影響を与えています。
少子高齢化や核家族化の進展に伴い、大規模な住宅の需要は減少傾向にあります。
一方で、在宅ワークの普及や趣味を楽しむためのスペースの確保など、新たなニーズも生まれています。
そのため、各世帯のライフスタイルに合わせた、最適なお家の広さを検討することが重要です。
4::世帯収入と住宅取得費用の関係
世帯収入によって購入または建築できる住宅の規模は変わります。
世帯収入が少ない世帯では、住宅取得費用を抑えるために坪数を小さくする傾向がありますし、世帯収入が多い世帯ではより広い住宅を検討できる可能性が高まります。
住宅ローンの支払いなどで日々の生活が厳しくならないよう、しっかりと資金計画を立てる必要があります。

まとめ
日本の戸建て住宅の平均坪数は2023年度時点で約36坪程度ですが、地域差や家族構成、予算、ライフスタイルなど、様々な要因によって大きく変動します。
今後も30坪を目指して年々小さくなっていくことが予想されます。
理想の住宅を実現するためには、平均坪数にとらわれず、自身のニーズを明確化し、土地面積や予算とのバランスを考慮しながら、最適な広さを検討することが重要です。
将来的なライフスタイルの変化も視野に入れ、柔軟に対応できる間取りや設計を選ぶことも大切です。
山形で注文住宅を建てるなら白田工務店へお任せください!
白田工務店では「基本性能重視」の家づくりを大切にし、安全・安心、長持ち、健康・快適・省エネの3つの視点から、お客様に価値のある住まいをご提案しています。耐久性が高く、高気密・高断熱で省エネにも優れ、夏の暑さや冬の寒さが厳しい山形でも快適に暮らせる家づくりをお手伝いします。
「一生に一度の家づくり」だからこそ、デザインだけでなく、住み続けるほどに実感できる快適さと性能を重視し、ご家族の未来を支える住まいをご提案します。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
電話でのお問い合わせはこちら:0237-83-9522(受付時間 8:00~17:30/日曜定休)
WEBからのお問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム(24時間受付)
モデルハウスについて:モデルハウス詳細ページ





