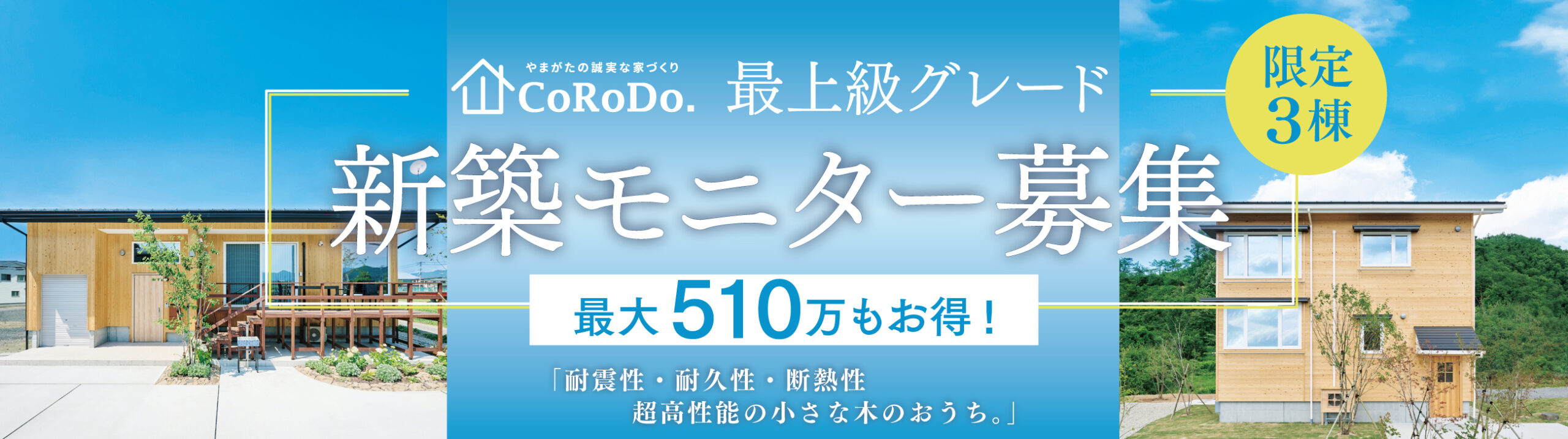2025年から変わった省エネルギー基準の法制度。
注文住宅を建てるなら、断熱性能は重要な検討事項といえます。
新基準では断熱性能の基準がどのように変更され、それが住宅建築にどのような影響を与えるのか、具体的に見ていきましょう。
2025年注文住宅の断熱性能等級はどう変わった?
2025年以降の断熱・省エネ法制度の変更点
2025年以降、住宅の省エネルギー基準が改正されました。
断熱等級4が義務化されたのです。
これまで断熱性能等級という基準は存在していたものの、それが法的な義務とはなっていませんでした。
今後は断熱等性能等級4以上とすることが法律で定められ、その計算書等の提出も必要となりましたので、より断熱性能の高さに対する意識が醸成されていくことでしょう。
等級4・5・6・7の具体的な断熱性能値(UA値など)
等級4、5、6、7それぞれのUA値は地域によって異なりますが、山形県が関係する4地域・3地域においては以下の通りです。
(酒田市の一部にのみある5地域は割愛)
【4地域のUA値】
※山形県の中でも一般的な地域
・等級4:0.75
・等級5:0.60
・等級6:0.34
・等級7:0.23
【3地域のUA値】
※山形県の中でも寒い地域
・等級4:0.56
・等級5:0.50
・等級6:0.28
・等級7:0.20
法的な義務となった等級4は、どちらの地域でもそれほど厳しい数値ではありませんので、法改正への対応は特に難しいことは何もないといえるでしょう。
住宅の形状、窓の大きさや種類、外壁や屋根の断熱材の種類と厚さなど、さまざまな要素がUA値に影響を与えます。
そのため、設計図面に基づいた綿密な計算が必要不可欠です。
そして、断熱性能を確保する上で、設計段階での的確な判断と、施工段階での丁寧な作業が求められます。
断熱等性能向上による住宅価格への影響
断熱等性能等級を上げるためには、より高性能な断熱材を使用したり、断熱層の厚さを増やしたりする必要があり、その分、建築費用は高くなる傾向にあります。
そしてそのかかり増し費用は、等級が上がるごとに多大なものとなっていきます。
例えば、等級4から等級5へ上げる場合、十数万円の追加費用で充分対応可能でしょう。
等級5から等級6へ上げる場合は追加で40~50万円ほどの費用がかかるでしょう。
しかし、高断熱住宅は光熱費の削減効果も大きいため、長期的な視点で見れば、初期投資に見合うだけのメリットが期待できます。
加えて、資産価値の向上も期待できるでしょう。
後から断熱性能を上げようと思っても、ほぼ実現不可能なほどの費用がかかります。
新築時になるべく断熱性能を上げておくことが、快適に過ごしつつ光熱費も大きく削減するためのベストタイミングであることを理解しましょう。
断熱性能向上による建築期間への影響
断熱性能を高めるための施工には、より高度な技術と時間を要することがあります。
そのため、断熱性能等級を上げることで、建築期間が若干長くなる可能性も考慮する必要があります。
とはいえ、これは工期の遅延につながるのではなく、より精密な施工を行うための時間確保と捉えるべきでしょう。
例えば等級6の住宅とする際、多くの場合では外周部へ付加断熱の工事が必要となります。
付加断熱の施工には概ね3~4日ほど工程が多く必要にはなりますが、大きな工程の違いとはいえないでしょう。
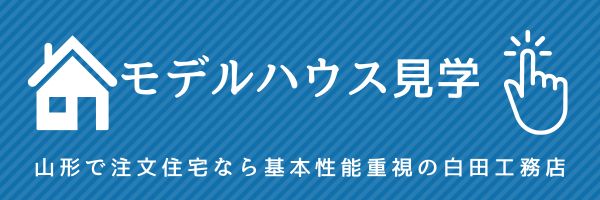
高断熱住宅を目指すには
高性能な断熱材の費用対効果比較
高性能な断熱材は、初期費用は高くなりますが、長期的な視点で見れば光熱費削減によるメリットが大きいため、費用対効果は高いと言えます。
さまざまな断熱材の価格や性能を比較し、予算と性能のバランスを考慮した選択が重要です。
ライフサイクルコスト全体で考えることが大切です。
断熱材の種類によるメリット・デメリットと適材適所
さまざまな断熱材にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
例えば、グラスウールは価格が比較的安価で施工しやすい一方、厚さあたりの断熱性能が他の高性能断熱材に劣ったり、雨水による水濡れに弱いという面もあります。
フェノールフォーム系のボード断熱材は、厚さあたりの断熱性能が非常に高く水濡れにも多少は抵抗できるというメリットがある一方で、断熱性能あたりの価格が高いというデメリットもあります。
それぞれの特性を理解した上で、最適な箇所に最適な断熱材を選択することが大切です。
例えば弊社の場合、水濡れを心配せずに施工可能な充填断熱の部位には高性能グラスウールを使用し、天候不順で水濡れの心配がある付加断熱の部位にはフェノールフォーム系ボード断熱材を使用するなど、適材適所で断熱材を選定しています。

断熱性能のポイント
断熱性能を上げるメリットデメリット
断熱性能を上げるメリットは、光熱費の削減、安価なランニングコストでの快適な室温の維持、などです。
一方でデメリットとしては、初期費用が高くなることが挙げられます。
メリットとデメリットを比較し、将来的な費用対効果を考慮した上で判断する必要があります。
目先の高い安いだけで選ぶのではなく、長期的な視点で住宅性能を捉えることが重要です。
光熱費削減効果のシミュレーション
断熱性能を高めることで、どれくらいの光熱費削減効果が期待できるのかをシミュレーションすることができます。
さまざまなシミュレーションツールや専門家のアドバイスを活用することで、より具体的な数値を把握し、計画に反映させることが可能です。
シミュレーション結果は、住宅設計の重要な判断材料となります。
補助金の活用方法
高断熱住宅の建築には、国や地方自治体から補助金が支給される場合があります。
これらの制度を活用することで、建築費用を抑えることができます。
それぞれの制度の条件や申請方法を確認し、積極的に活用することが重要です。
また、申請時期や必要書類なども事前に確認しておきましょう。
高断熱住宅に強い建築会社を見極めるポイント
実績と経験豊富な建築会社の選び方
高断熱住宅の建築実績が豊富で、高い技術力を持つ建築会社を選ぶことが重要です。
過去の施工事例や顧客からの評判を確認し、信頼できる会社を選ぶようにしましょう。
実績は、建築会社の信頼性を判断する上で重要な指標となります。
また、断熱性能だけに詳しくてもダメ。
防湿層の施工はどのようにしているか、気密性能への気配りはどうか、耐震性能についての考えはどうかなど、総合的な住宅性能への造詣の深さが重要となるのです。
高断熱住宅の施工事例を確認する方法
建築会社のホームページやパンフレット、住宅展示場などで、高断熱住宅の施工事例を確認することができます。
実際に完成した住宅を見学することで、建築会社の技術力や施工品質を評価することができます。
見学の際には、断熱材の種類や施工方法なども確認すると良いでしょう。
建築会社との適切なコミュニケーション方法
建築会社とのコミュニケーションを密にすることで、要望を的確に伝え、納得のいく住宅を建築することができます。
設計段階から完成まで、積極的にコミュニケーションを取り、疑問点や不安点を解消していくことが大切です。
良好なコミュニケーションは、理想の住宅を実現するための重要な鍵となります。
まとめ
2025年からは法改正によって住宅の断熱等性能等級4が義務化され、より高い断熱性能が求められる時代に突入します。
ひと昔前まで、「断熱等性能等級4は最高等級だった」のです。
それが「たった数年で最低基準」となったことは注目に値します。
今後2030年頃に予定されている法改正では、等級5が最低基準として義務化される未来も見えてきています。
今後UA値の基準がさらに厳しくなり、等級5、等級6以上が主流となることで、高断熱化が一層進むことが予想されます。
長期的な視点で費用対効果を考慮し、将来の新基準にも適合可能な住まいづくりを目指すことが、安心で快適な暮らしにつながるでしょう。
山形で注文住宅を建てるなら白田工務店へお任せください!
白田工務店では「基本性能重視」の家づくりを大切にし、安全・安心、長持ち、健康・快適・省エネの3つの視点から、お客様に価値のある住まいをご提案しています。耐久性が高く、高気密・高断熱で省エネにも優れ、夏の暑さや冬の寒さが厳しい山形でも快適に暮らせる家づくりをお手伝いします。
「一生に一度の家づくり」だからこそ、デザインだけでなく、住み続けるほどに実感できる快適さと性能を重視し、ご家族の未来を支える住まいをご提案します。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
電話でのお問い合わせはこちら:0237-83-9522(受付時間 8:00~17:30/日曜定休)
WEBからのお問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム(24時間受付)
モデルハウスについて:モデルハウス詳細ページ