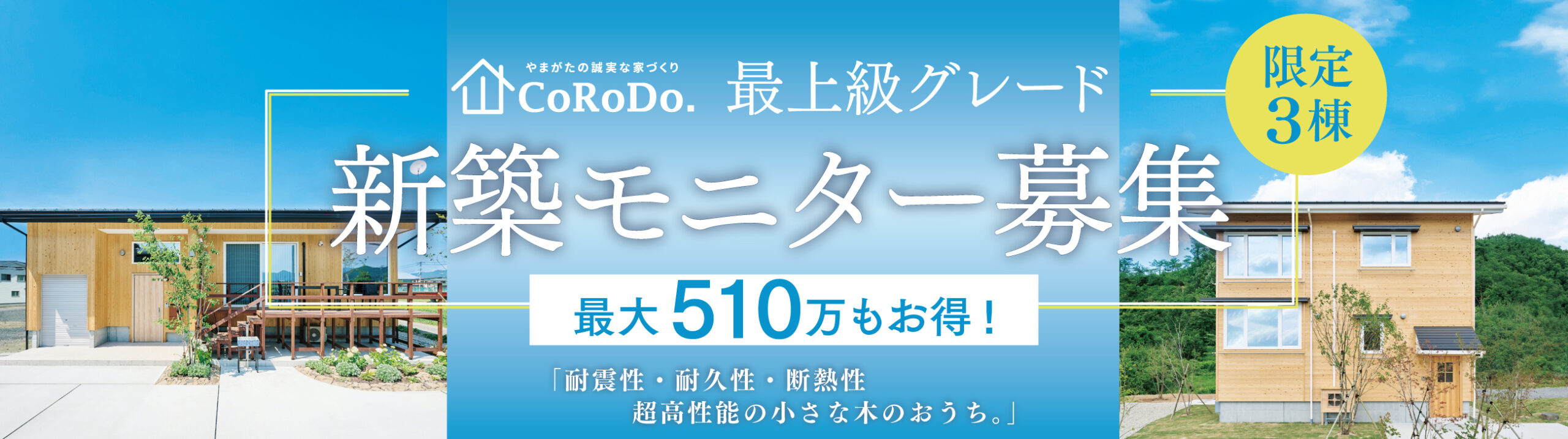トイレは日常生活において誰もが使う設備であり、快適性・安全性・利便性が求められる空間です。
しかし、その設計が不十分であると、高齢者や障がいのある方にとっては危険やストレスの要因になります。
特に日本では高齢化が進み、「すべての人にとって使いやすいトイレ」が重要なテーマとなっています。
本記事では、人間工学に基づいたトイレ空間の大きさや、ユニバーサルデザイン・バリアフリーの観点から、誰もが快適に使用できるトイレ設計について詳しく解説します。
トイレ空間の基本寸法
人間工学に基づく設計の考え方
人間工学では、人が自然な姿勢・動作で設備を利用できることが重要です。トイレ空間でも「立ち座りの動作」「体の回転」「補助具の使用」などを考慮する必要があります。
たとえば、便器の中心から壁までの距離が狭いと、体を十分に動かせず、転倒のリスクが高まります。十分なスペースがあれば、介助者の動作もスムーズになり、安全性が高まります。
一般的な家庭のトイレサイズとは?
日本の一般的な家庭用トイレの室内有効寸法は以下の通りです。
・幅(内寸):約80~90cm
・奥行き:約120~160cm
・天井高さ:約200~240cm
これらは最低限の寸法であり、快適性や安全性を考慮するとより広いスペースが望まれます。

ユニバーサルデザインとバリアフリーの視点から見るトイレ設計
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い
バリアフリー:既存の障壁を取り除く設計のことで、高齢者や障がい者など特定の人が生活しやすい仕様の設計やデザインのことを指します。
ユニバーサルデザイン:最初から誰でも使いやすい設計のことで、子ども・高齢者・健常者すべての人が等しく使いやすいように考えられています。
つまり、バリアフリーは「困っている人に合わせて改良する」アプローチであり、ユニバーサルデザインは「最初からすべての人にやさしい設計を目指す」ものです。
ですので、住宅のトイレは住む人に合わせて、ユニバーサルデザインとバリアフリーの良いところを組み合わせると、家族全員が使いやすい空間となるでしょう。
高齢者・障がい者・子どもへの配慮
以下は使用対象ごとに考えられるトイレ空間の工夫ポイントになります。
・高齢者向け:立ち上がりをサポートする手すり、滑りにくい床材、やや高めの便座(40〜45cm)
・障がい者向け:車いす対応の広いスペース、移乗しやすい便器配置、低位置の設備スイッチ
・子ども向け:低い位置にある洗面器・ペーパーホルダー、安心できる照明
子どもを対象にした工夫は、成長後に使いにくさを感じてしまう場合があるので、長期的な目線とメリット・デメリットを考えた上で導入しましょう。
車いす対応トイレの設計基準
車いすを使用する生活空間では、一般のトイレよりも広さが必要です。以下は、車いすで問題なく活動するための最低限の空間寸法(JIS規格(JIS S 0026))となります。
・回転スペース:直径1,500mm以上
・便器横の移乗スペース:便器から壁まで800mm以上
・便器前方のスペース:1,200mm以上
・出入口の有効幅:800mm以上
使用する車いすによってはサイズも異なるため、上記のサイズでは狭い可能性もあります。利用者に合わせて柔軟な設計をする必要があるでしょう。
レイアウトの注意点
手すりや出入り口、設備の配置など、日々の行動をスムーズにするためには細かなレイアウトの工夫が必要になってきます。
・ドアは引き戸または外開きが基本(内開きだと転倒時に救助困難)
・手すりや便座の高さ、位置が使用者の体格に合っているか
・緊急呼び出しボタンの見やすさと押しやすさ
日常的によく使う場所だけではなく、緊急時に使用するような物、場所についてもしっかり計画して設計に反映させておくことをお勧めします。
人間工学に基づく手すり・設備の配置
人間工学的配慮とは?
人間工学では「人の身体寸法・力の使い方・視野・反応速度」などに基づいて、設備の位置や形状を決定します。これにより、無理な姿勢や動作を避け、安全で疲れにくいトイレ利用が可能になります。
手すりの設置位置と高さ
手すりは便器に座っている状態から立ち上がる時に使用することが多いため、手すりの位置は便器の横で床から高さ750mm前後(最低でも650mm以上が望ましい)、便座から200〜300mm離れた場所だと使い勝手が良いでしょう。
この位置は便器に座っている時の肘の高さや肘から手までの長さが関係しています。
とは言え、人によって体型は様々なので、住む人たちに合わせて手すりを取り付けるのが良いでしょう。
また、紙巻器や洗浄ボタンの位置についても、手すりと同様に座った状態での腕の可動域内で、使用しやすい位置に配置するのがベストです。
<参考サイト>
以下は高齢者を対象としてた手すりの高さに関する調査データです。
(一般社団法人 人間生活工学研究センター)
今後のトイレ空間設計のトレンド
トイレも開発が進んでおり、色々な面で機能的になってきています。
また、最新技術を取り入れたトイレも開発されているなど、次世代型の商品が次々と生まれているようです。
スマートトイレとIoTの活用
・自動開閉・自動洗浄・自動除菌などのスマート機能
・センサーで健康データ(便の状態、尿検査、血圧など)を取得する研究も進行中。一部実用化済
サステナブルな素材と省エネ
・節水型トイレやタンクレストイレ
・再生可能素材や抗菌素材の活用
多機能と省スペースの両立
・狭い空間でも使いやすいレイアウトの工夫
・壁面収納や折りたたみ式の手すりなど、省スペースと機能性の両立
まとめ
トイレは「誰もが毎日使う空間」であるからこそ、その設計には深い配慮が求められます。人間工学に基づいた寸法設計、ユニバーサルデザインの考え方、そしてバリアフリーへの対応を意識することで、すべての人にとって「安全・快適・使いやすいトイレ空間」を実現することができます。
トイレ設計を検討する際は、建築士などと相談しながら、実際の利用者の視点で考えることが大切です。場合によって、手すりなどは建築現場で直接確認し調整することも可能です。
この記事が、より良いトイレ空間づくりの参考になれば幸いです。